【渋谷の弁護士が解説】離婚届にサインしてしまったが、離婚したくなくなった場合にはどうすべきか?
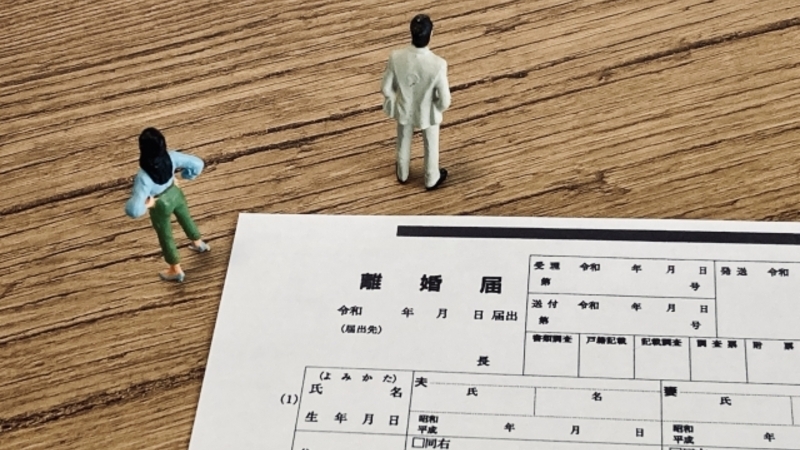
目次
はじめに
渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を運営している弁護士の馬場洋尚と申します。本コラムでは、一度は合意して離婚届にサインしたものの、やはり離婚したくないと考え直した場合に、どのような法的手続きを取るべきかについて解説します。
離婚が成立するための要件
協議離婚が法的に有効となるためには、以下の二つの要件を満たす必要があります。
離婚意思の合致:夫婦双方に離婚する意思があること。
離婚届の提出と受理:離婚届を作成し、役所に提出して受理されること。
重要なのは、離婚意思が「離婚届が役所に受理される時点」まで存在し続けなければならないという点です。したがって、離婚届に署名・押印した時点では離婚に同意していても、その後考えが変わり、役所に提出される前に離婚の意思を撤回した場合には、その離婚は無効となります。
離婚届がまだ提出されていない場合―不受理届を提出する
相手が離婚届を提出する前であれば、離婚を防ぐための有効な手段があります。それが「離婚届不受理申出制度」の利用です。
⑴ 不受理申出制度の概要
不受理申出制度とは、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防ぐために設けられた制度です。事前に市区町村の役所に「離婚届不受理申出書」を提出しておくことで、もし相手方が一方的に離婚届を提出しても、役所がその受理を阻止してくれます。この制度は、届出によって法律行為が成立する離婚、婚姻、縁組、離縁などに適用され、中でも離婚届の不受理申出が最も多く利用されています。
⑵ 不受理申出の手続き
不受理申出は、「離婚届不受理申出書」を市区町村の役所に提出することで行います。提出先は、申出人の住所地または本籍地の市区町村役場です。ただし、本籍地でない役所に提出した場合、その情報が本籍地の役所に通知されるまでに時間がかかることがあります。その間に相手が本籍地の役所に離婚届を提出してしまうと、不受理申出の情報が届いていないため受理されてしまうリスクがあります。そのため、本籍地の役所に提出するのが最も確実です。
⑶ 不受理扱いをする期間―無制限
かつて不受理申出には6か月の有効期間が定められていましたが、2007年の戸籍法改正により、有効期間は撤廃されました。したがって、一度不受理申出をすれば、後述する「取下げ」を行わない限り、その効果は永続します。
⑷ 不受理申出の取下げ
不受理申出の効果は、申出人が「取下書」を提出して取り下げない限り継続します。将来、再び離婚に合意し、離婚届を提出する際には、この取下げの手続きが必要になります。
⑸ 不受理申出をしていたにもかかわらず誤って受理された場合
万が一、不受理申出をしていたにもかかわらず、役所のミスで離婚届が受理されてしまった場合でも、その離婚が直ちに無効と判断されるわけではありません。離婚の有効性を争うためには、後述する離婚無効確認の手続きと同様に、最終的には裁判所の判決等によって戸籍を訂正する必要があります(東京高等裁判所決定昭和42年12月13日・家裁月報20巻6号25頁参照)。
離婚届がすでに提出・受理されてしまった場合
離婚届がすでに役所に受理されてしまった後で離婚の意思がなかったことに気づいた場合でも、諦める必要はありません。法的には、届出の時点で夫婦の一方に離婚意思がなければ、その離婚は無効です。たとえ自分の署名・押印がある離婚届であっても、提出時点までに離婚の意思を失っていたのであれば、同様に無効となります。
しかし、離婚が無効であっても、役所は届出の際に当事者の意思確認まで行わないため、戸籍上は離婚が成立した状態になってしまいます。この戸籍の記載を訂正するためには、家庭裁判所での手続きが必要です。当事者同士で「離婚はなしにしよう」と合意するだけでは、戸籍の記載を元に戻すことはできません。
具体的な手続きは以下の通りです。
離婚無効確認の調停申立て:まず、家庭裁判所に「離婚無効確認調停」を申し立てます。これは、話し合いによって離婚の無効を確認する手続きです。
合意に相当する審判:調停において、当事者双方が離婚の無効(例:届出時に離婚意思がなかったこと)について争わず、無効とすることに合意している場合、家庭裁判所は事実を調査した上で「合意に相当する審判」をすることがあります。この審判が確定すれば、離婚は無効だったと法的に確定します。
離婚無効確認の訴訟提起:相手が離婚の有効性を主張するなどして調停で合意に至らない場合、調停は不成立となります。その場合は、地方裁判所に「離婚無効確認の訴え」を提起し、裁判で離婚の無効を主張・立証していくことになります。訴訟で離婚無効の判決が確定すれば、離婚は当初からなかったことになります。
これらの手続きを経て離婚の無効が確定した後、判決書や審判書を添付して市区町村の役所に戸籍の訂正を申請します。
なお、相手に騙されたり、脅されたりして離婚届の提出に応じてしまった場合は、「離婚の無効」ではなく「離婚の取消し」を求めることになります。取消しの手続きも調停・訴訟を経る点は同様ですが、詐欺を知った時または強迫を免れた時から3か月以内に請求しなければならないという期間制限があるため、注意が必要です。
まとめ
離婚届にサインをしてしまった後で離婚したくなくなった場合、取るべき対応は「離婚届が提出されたかどうか」で大きく異なります。
未提出の場合:直ちに市区町村の役所に「離婚届不受理申出書」を提出してください。これにより、相手による一方的な届出を防ぐことができます。
提出済みの場合:家庭裁判所に「離婚無効確認調停」を申し立てる必要があります。戸籍を訂正するには、調停や裁判といった法的な手続きが不可欠です。
いずれのケースでも、ご自身の状況に合わせて迅速に行動することが重要です。この問題でお悩みの方がいらっしゃいましたら、渋谷駅付近の馬場綜合法律事務所にお気軽にお問い合わせください。
この記事を書いた人

馬場 洋尚
(ばば ひろなお)
東京都出身。
令和元年12月、渋谷駅付近で馬場綜合法律事務所を開設。
法的問題の最良の解決を理念とし、離婚、相続、遺言、一般民事、企業法務など幅広く手がけています。その中でも離婚・男女問題には特に注力して活動しています。ご依頼者の方と密接なコミュニケーションを取りつつ、ひとつ一つのご案件に丁寧に接することを心掛けています。
